2015.12.02(水)事務局委員会メンバー紹介
参加型計画委員会メンバー紹介
毎月1名ずつ、委員会メンバーが活動にかける思い、自己アピール等をリレーしていきます。
“参加型計画委員会メンバー紹介” への24件のフィードバック
事務局 にコメントする
最新の記事
-
2024年12月27日
- 【お知らせ】令和6年度 講習会開催のお知らせ
- 参加型計画専門委員会講習会「多様化する社会変化に対応する市民参加型計画のあり方」 「参加型計画専門委員会」では、行政・市民・事業者等が協働して実施する新たな参加型計画のあり方と建設コンサルタントの役割...
-
2023年12月26日
- 【お知らせ】令和5年度 講習会開催のお知らせ
- 参加型計画専門委員会講習会 「多様化する社会変化に対応する市民参加型計画のあり方」 今回の講習会は、次の2点を目的とし、できるだけ多くの協会員への普及と周知のため、WEB開催の講習会を実施します。 ①...
-
2023年05月23日
- 講習会の報告(「多様化する社会変化に対応する市民参加型計画のあり方― 事例研究から ―」)
- 令和5年1月17日に、建設コンサルタンツ協会会員を対象に「多様化する社会変化に対応する市民参加型計画のあり方」に関する講習会を開催しました(一般:オンライン参加のみ)。 第1部では、当委員会から2つの...
-
2023年01月10日
- 【お知らせ】令和4年度 講習会開催のお知らせ
- 参加型計画専門委員会講習会 「多様化する社会変化に対応する市民参加型計画のあり方」 ― まちづくり分野におけるソーシャル・インパクトとその展開可能性 ― 1. 開催日 令和5年1月17日(火) 14:...
-
2021年12月07日
- 【お知らせ】令和3年度 講習会開催のお知らせ
- 「多様化する社会変化に対応する市民参加型計画のあり方」 ― 事例研究から ― 当委員会では、今期から、これまでの取組みをベースに、行政・市民・事業者等が協働して実施する新たな参加...
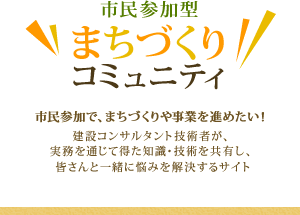




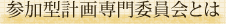



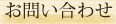


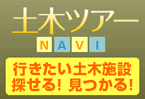
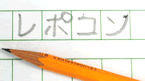
私はこれまで都市計画・交通計画といった分野で、市民参加による具体的な計画策定や地域交通のマネジメントに係わるような業務を多く担当してきました。
最近では社会資本整備における様々な局面において、市民参加が当たり前のように求められてくるようになってきました。しかし、市民の価値観は当然ながら個人や地域によっても異なりますし、時代や社会情勢によっても常に変化していくものと考えられます。
そのため、市民参加のまちづくりをその場限りのものにするのではなく、継続的な活動に繋げていくことこそが重要だと考えるようになってきました。
この参加型計画委員会には、日本各地で様々な経験を積んできた参加型計画のエキスパートが集まっています。また、委員会活動を通じて、たくさんの外部の方との交流も増えてきています。参加型計画によるまちづくりの未来について、皆さんとの議論を通じて一緒に考えていけたらと思っています。
外山 秀人 より
私は入社以来、交通計画や都市計画の分野に携わり早くも23年が経ちました。
私が市民参加による合意形成に取り組みだしたのは、確か平成12年頃だったと記憶しています。対象はあるダムの周辺環境整備で、公園や交流施設の整備について、地元の方とワークショップを5回/年ほど実施しました。またまだ駆け出しだった私は1回だけファシリテーターを任され、すごく緊張していっぱいいっぱいになったのを覚えています。
いまや市民参加による合意形成も当たり前のようになってきており、私自身も今では合意形成のなかでの様々な問題に対してもある程度、的確に対応できるようになってきました。
とは言いながら、今でも住民の方々に教えられることも多く、日々、円滑な合意形成に向けたスキルや技術者としての心持を磨き続けている次第です。
この参加型計画専門委員会は、様々な分野の技術者が集まり、円滑な合意形成による暮らしやすい社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいる集団です。お困りことなどがあれば、気軽に相談してください。きっと解決のヒントが見つかるはずです。
私は建築・都市計画分野の研究を志し、2006年に日本に留学、学業が終えたあとも引き続き日本に残り都市計画・まちづくりの現場に携わっております。近年の日本のまちづくり及び都市開発は複合化・多目的化が進み、行政・民間・住民など様々なステークホルダーの参加と合意形成が必要となってきております。
参加型委員会では、超高齢化社会・人口減少など課題先進国と呼ばれる日本のまちづくりにおいて、多様な主体が力を合わせてまちの課題を解決するための仕組みづくりを支援するとともに、そこから得られた知見を世界に展開していきたいと考えております。
そのためには、皆さまからのいろんなご意見やご知見をいただきながら日本のまちづくりを考えていきたいと思います。
公園緑地を中心に道路空間や河川空間を活用したまちづくり等、計画から設計、運営に至る多様な業務に携わってきました。
従前の市民参加のあり方は、公共事業への理解を得るために市民ニーズを汲むことへ重きを置く傾向にもありました。しかし近年では地域の活性化を視野に歴史や文化や歴史、使いやすさなど質の向上に加え、防災やメンテナンスへの参画、更には多様な主体による収益性も求められる中、一層重要な位置づけとなります。
市民参加の有益性や必要性は認められる一方で、煩雑性や効率性への懸念から回避したい現実もあります。市民参加のあり方とコンサルタントの対応を議論する当委員会において、より広範な知見が共有できればと思います。
橋本 亮 より
私は、入社以来、都市計画や交通計画の分野の様々な業務に携わってきました。
市民参加による合意形成に関しては、バリアフリー整備にあたり、地域の身体障碍者の方々に参加いただき、まち歩きを行い、様々なご意見をお聞きしたのが、最初であったと記憶しています。しかし、当時は、新入社員であり、人の意見に耳を傾けるより、業務の中で自分に与えられた役割をこなすことで精一杯でした。
その後も、バリアフリーをはじめ、公共施設等のデザイン設計や景観計画、コミュニティバスの導入などといった業務において市民参加のワークショップなどを開催し、私自身もファシリテーターとして貴重な経験を積ませていただいております。
近年は、計画策定の途中で意見を言うだけの参加ではなく、住民が主体となって、まちづくりを進めていく場面が多くみられ、そのための制度も整えられてきています。
この参加型計画専門委員会には、私より遥かに多くの経験や実績、知識を有する技術者が集まっています。そのような方々と一緒に、新たな市民参加のあり方とコンサルタントとしての対応について議論を重ね、一人の技術者として、学び、そして、現場に還元できるよう努めてまいりたいと思います。
牧野 幸子 より
私は、昨年9月末にめでたく定年を迎えました。定年の次の日から同じ職場で働かせていただいています。38年間、猛烈に忙しいこの業界で二人の子供をよく育てたと思います。主人は子供達が小学校に入る頃から海外出張や単身赴任と殆ど母子家庭の状態でした。現在、子供が巣立ち夫婦二人の生活です。平日は、私の帰宅時間が遅いので主人が夕食の支度をしてくれます。
家庭のことはさておき、私は、道路計画とまちづくり計画を専門にしています。道路計画の生活道路の交通安全対策では、住民とともに、街歩き点検、ワークショップ、社会実験などを行いながら対策案を検討します。まちづくり計画では、住民とともに同様の手法を実施し、広報活動などを行いながら計画案を検討します。テーマは異なっていても、参加型計画は、考え方や感じ方の異なる方々とともに、より良い方向性を見つけていく面で同じだと考えます。参加型計画を実施することで、住民の相互理解や交流が生まれるなどの効果も期待できます。現在、当委員会では、幅広い参加型を対象にしています。時間と手間がかかることから、参加型計画の実施数は少ないですが、今後様々な分野で導入され推進されるように、委員会活動において検討していきたいと考えています。
山岸 勉 より
私は2016.7に定年退職を迎え、継続雇用で同じ職場で働いています。実は、50歳を過ぎてのご縁あっての転職でした。前職は水環境専門のコンサルタントで、私は水理模型実験や河川構造物の計画・設計に携わっていました。災害復旧で旧建設省の地方事務所に一年間出向もしました。私事ですが、そこで妻と知り合い結婚しました。当時80年代末はバブルの弾ける前で、ふるさとの川モデル事業を担当していたこともあり、目の回る忙しさでした。リバーフロント整備センターの諸先輩方や横浜市のNPOの方々とご縁ができました。河川空間とまちづくりが融合しあう熱い時代でした。私事では子どもも生まれ、後ろ髪を引かれながら日曜出勤したのも今では懐かしい思い出です(働き方改革とは真逆の時代でした)。
90年代中頃には河川財団に出向し、清流ルネッサンスやいい川づくりなどの新しい河川管理の仕組みづくりに従事しました。現在の職場に移ってからは、東日本大震災による海岸構造物の災害復旧などを担当した後、現在は風力発電や木質バイオマスなどの再エネによる地域創生に取り組んでいます。専門委員会は毎回、委員の得た新しい知見や情報に触れることができ、いつも刺激を受けています。この拙文を読んでいただけたあなたも、いつか同じ委員会の仲間に入っていただければ望外の喜びです。
横山 哲 より
35年前に新卒採用でこの業界に入り、橋梁設計を皮切りに技術開発、道路計画、道路設計などの分野を渡り歩いてきました。この間、業界を取り巻く状況は、大きく変化しました。特に、道路整備や地域開発にあたり、景観を重視したり、利用者の利便の面からバリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入など、かつては標準的な設計や仕様でつくることの効率を重視せよといわれていたものが、市民の意見を聞き取り地域に適した仕様、さらに使い勝手の良い仕様に向けた努力がされる場面が増えてきています。この委員会を設立した14年ほど前は、「パブリックインボルブメント」「住民参加」といったキーワードが出始めたときでした。この流れの中で、交通安全対策としてのコミュニティゾーン形成事業や交通バリアフリー法成立後の計画づくりのワークショップを運営し、多様な視点を持つことでよりよい社会資本整備が出来ることを実感しました。その後、様々な業務で市民参加の場を運営し、市民の社会資本整備のプロセスへの参加が重要なこと、そのうえで参加者が「腑に落ちる」計画づくりが重要なことを学びました。いま、時代はインフラマネジメントや観光まちづくり、手段としてモビリティのシェアなど、これまでとは異なる課題を解決しなくてはならなくなっています。多くの関係者がプレーヤーとなって社会を支えていく、その主役である市民が個々の役割を楽しく果たせるような環境づくりを行っていくのが、我々の務めであると考えています。
私はこれまで主に交通計画、道路計画・設計の業務に携わってきました。
思い返せば、就職にあたってコンサルタントを志望したのは、街に自分の計画・設計したインフラを残す仕事がしたい、そんな思いでした。学生時代の私は、インフラが世に形となって出来上がるまでに、これほどまでにたくさんの方々が関わっていることを理解していなかったため、就職して、インフラの計画・設計プロセスには膨大な過程があることを知り、公共施設を作ることの重みを痛感したことを覚えています。
それでも、今思い返せば、その当時はまだ行政の意向のみが反映されたインフラづくりがほとんどだったかと思います。時代は変わり、あらゆる場面で市民参加が求められるようになってきています。コンサルタントにも市民の声を聞き、市民の目線で考え、時には市民の力も借りながら、よいまちを作るということが求められるようになってきており、まだまだ勉強しなければいけないことが山積みだと感じています。
日常業務の中では、参加型の業務に従事する機会はさほど多いわけではないですが、参加型の業務かどうかにかかわらず、上記のような視点は絶えず持ち、地域の方々に喜んでもらえる町を作る仕事に携わっているという気概をもってこれからも努力していきたいと思います。
渡辺 茂樹 より
私は、平成元年に新卒でこの業界に入り、交通計画、道路計画の技術者として、平成の時代を駆け抜けてまいりました。入社当時は「参加型計画」という言葉すら聞いたことが無く、平成8年頃、当時の建設省が「パブリックインボルメント(PI)」という言葉を発した頃から、興味を持つようになりました。私が参加型計画に本格的に携わるようになったのは、平成12年頃だったと記憶しています。高速道路のインターチェンジの計画予定地の土地利用計画で、将来のまちのあり方について、地域の方々と10回ほど実施しました。まったく未経験だった私が、今でいう「ファシリテーター」を任され、地域の方々の意見をまとめるのに四苦八苦したことを覚えています。
参加型計画を取り巻く環境は日々変化しており、この参加型計画委員会の活動に関わった15年前は、都市計画マスタープランや緑の基本計画、公園や駅前広場といった都市施設の計画づくりを市民の意見を取り入れて行うことが主体でした。現在では、防災分野、福祉分野など幅広い分野で用いられ、参加型計画の重要性が高まっていることを実感しています。最近の委員会活動では、「資金面での参加」についても参加型計画の一部と捉え、事例収集をはじめ、まちづくりへの適用性について勉強しているところです。この資金調達も含め、参加型計画における建設コンサルタントの存在意義を高めていきたいと思います。